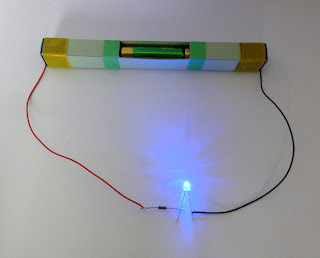冬場や乾燥した日には厄介な「静電気」
この静電気を使って、楽しい実験をしてみましょう。
まずは最も簡単に出来る 「静電気で追いかけっこ」です。
①6mmφのストローの曲がる部分を切り離し
長い方の真ん中に一つ穴パンチで穴を開けます。
②ストローの両端にアルミ箔の旗を貼り付けます。
アルミ箔は3~4cm程度のもので、先をとがらせておきます。
真ん中の穴にペンシルキャップの頭を入れます。
③竹串のとがっていない方をを発泡スチロールに刺し
とがった方に②のペンシルキャップをかぶせます。
(下の台は発泡スチロールでなくてもOKです。)
ビデオは2021年に作成し直したもので
アルミホイルの旗を三角と四角にし、
ストローの代わりに塩ビ製の板を使用しました。
塩ビ製の板をティッシュでこすると
塩ビ製の板はマイナスにティッシュはプラスに帯電します。
負になるか正になるかは
どの素材同士を接触させるかで決まります。
この帯電列の左の方が正に帯電しやすく、
右の方が負に帯電しやすいものです。
今回は塩ビ製の板をティシュペーパーでこすったので、
塩ビ板は負に帯電しました。
今回の実験ではまず、電気的に中立なアルミホイルに
負に帯電した塩ビ板を近付けました。
アルミホイルはゆっくりと塩ビ板に引き寄せられます。
次に点や線でちょこっと接触させると電子が移動し
アルミ箔はマイナスに帯電します。
また、接触させなくてもかなり接近させた場合には放電によって電子が移動します。
アルミ箔も塩ビ製の板も負に帯電した状態となり、
アルミ箔は塩ビ製の板から逃げていきます。
より多くの電子を移動させようと、
塩ビ板とアルミホイルの面同士を接触させると・・・
あれ?全く反発しない!ってことがあります。
この場合には下図のようなことが発生していると考えられます。