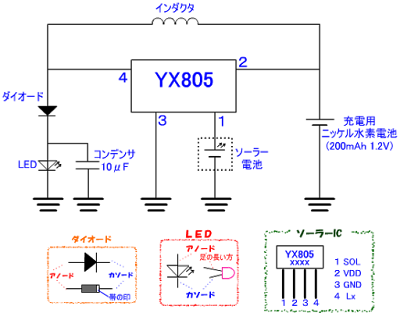今ではすっかりお馴染みの、100円ショップのソーラーガーデンライト。
庭に立てておくと、昼間にソーラーから二次電池に充電し
夜にLEDが点灯します。
光センサーなどで照度を感知して
暗くなるとLEDが点灯するの?って思いきや
暗くなるとLEDが点灯するの?って思いきや
ソーラー電池から基板に流れる電流で制御しているようです。
また中を開けると、1.2Vのニッケル水素電池が1個だけ。
これでLEDを点灯させています。
(LEDは順方向電圧の最も低い赤色でも1.7V以上の電圧が必要です。)
制御用のIC1つで、
①ソーラーからの入力電流の強弱でLEDをオンオフさせる。
②暗ければ1.2VでLEDを高速点滅させる。(発振回路)
①ソーラーからの入力電流の強弱でLEDをオンオフさせる。
②暗ければ1.2VでLEDを高速点滅させる。(発振回路)
商品によって、使われている基板が異なっていたり、
付属の二次電池の形が違ったりしますが、
基本的な仕組みは同様のようです。
今回使用したのは
中には単4のニッケル水素電池(1.2V 200mAh)が入っています。
ちなみにダイソーで1個100円の単4のニッケル水素電池(ReVOLTES)は
制御用のICはYX805が使用されています。
YX805のデータシートはこちらです。
改造前の製品は このように接続されています。
<改造その1>
7色に変化するLEDを光らせる。
この基板でLEDを点灯させた場合、
LEDの端子電圧は下のようにオンオフを高速で繰り返しています。
製品についてる白色LEDを7色に変化するイルミネーションに取り換えても
常に最初の1色 (赤色) しか光りません。
製品についてる白色LEDを7色に変化するイルミネーションに取り換えても
常に最初の1色 (赤色) しか光りません。
ではどうすれば、7色に光るLEDを点灯させることが出来るか?は
データーシートの右下に書いてあります。
整流用のダイオードは順方向降下電圧の低い
ショットキーバリアダイオードを使用しました。
(整流用ダイオード1N4007でも光りますが、光り方が弱いです。)
私の手持ちのダイオードでは、
ショットキーバリア ≒ ゲルマニウム > 高速スイッチング>1N4007
の順でいい感じでした。見た目だけの感じですが・・・)
私の手持ちのダイオードでは、
ショットキーバリア ≒ ゲルマニウム > 高速スイッチング>1N4007
の順でいい感じでした。見た目だけの感じですが・・・)
コンデンサ10μFはセラミックコンデンサを使用しました。
コンデンサがなくても、7色に変化しますが電圧は変動しています。
(下の波形図を見て下さい。)
①
基板からLEDを切り離し、ミノムシクリップを繋ぎます。
②
その他はブレッドボードで組み立てました。
コンデンサありの場合のLEDの端子電圧です。
発光色によって電圧が変化します。
コンデンサなしの場合のLEDの端子電圧です。
発光色によって最大値、最小値、周波数が変化します。
コンデンサあり、なしともに同じように光っているように見えますが
波形は全然違いますね。
<改造その2>
暗くならなくてもスイッチオンで光らせる。
ソーラーガーデンライトの良さは
暗くなると自然に光りはじめる点かも知れませんが、
「1」からソーラーを外して、充電池に並列に接続します。
充電池からの逆電流防止のため
ショットキーバリアダイオードを直列に入れておきます。
①
ソーラー(白)、充電池(赤)ともに正極側のコードを切断
ソーラー側(白)にショットキーバリアダイオードのアノードを直列に接続
充電池からの逆電流防止のため
ショットキーバリアダイオードを直列に入れておきます。
①
ソーラー(白)、充電池(赤)ともに正極側のコードを切断
ソーラー側(白)にショットキーバリアダイオードのアノードを直列に接続
<改造その3>
相互誘導でLEDを光らせる。
この基板は高周波発振(周波数 約270kHz )なので、
一次コイルは0.2mmφのポリウレタン銅線を20回
単1乾電池に巻き、抵抗100Ωを直列に接続しています。
抵抗がない方が明るく光るかも知れませんが、ないとインダクタが少し熱くなります。
抵抗がない方が明るく光るかも知れませんが、ないとインダクタが少し熱くなります。
二次コイルは0.1mmφのポリウレタン銅線を150~200回
単1乾電池に巻き、赤色と緑色のLEDを逆向きの並列接続にしています。
一次側コイルの端子電圧です。
二次側コイルの端子電圧です。
これ以外の実験や工作も掲載していますので、
こちらも見てみて下さい。