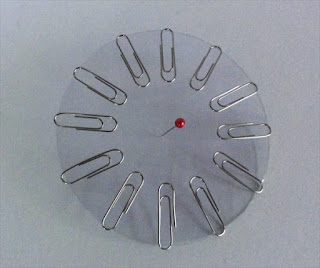高電圧発生装置を使って、フランクリンモーターの変形版を作ってみました。
高電圧発生装置の作り方は
http://eneene7.blogspot.jp/2016/10/blog-post.html
こちらを参照して下さい。
高電圧発生装置の作り方は
http://eneene7.blogspot.jp/2016/10/blog-post.html
こちらを参照して下さい。
①
材料を切り出します。(サイズは適当で構いません。)
・木材 (20cm×8cm、0.8cm角×8cm 2本)
木材部分は発泡スチロール他 どんな素材でもOKです。
・塩ビ板(硬質カードケース利用) (直径10cmの円形、0.8cm×5cm 2枚)
・発泡スチロール棒 (2cm角×6cm 2本) 木材でもOKと思います。
・ストロー (2cm 2本)
・リード線 (5cm 2本)
・アルミ箔 (1cm×5cm 2枚)
②
円形の塩ビ板の中心に待針を刺して、
周囲に12個のクリップを等間隔に挟みます。
(隣のクリップと接触させないよう、5mm以上は間隔をあける。)
③
0.8cm×5cmの塩ビ板の上の方に穴を開け(一つ穴パンチ利用)
木柱にセロテープで貼り付けます。
貼るときに、穴の位置を0.5~1mm程度、上下にずらしておきます。
④
木板の真ん中あたりに木工用ボンドで貼り付けます。
間隔は、待針の長さより5~10mmほど短めにします。
⑤
ボンドが乾いてから、②のローターの待針を
塩ビ板のパンチ穴に挿入します。
0.5~1mm程度高い方の柱に待針の球形部分を、低い方に針の部分を挿入します。
写真のように ほんの少し斜めになって待針の球で支える感じです。
⑥
電極を作ります。
アルミ箔 (1cm×5cm)の端の方にリード線 (5cm)の
被覆をはがした部分をテープで貼り付けます。
電極を作ります。
アルミ箔 (1cm×5cm)の端の方にリード線 (5cm)の
被覆をはがした部分をテープで貼り付けます。
⑦
これを発泡スチロール棒 (2cm角×6cm)の上部にテープで貼り付けます。
アルミ箔の先の方は少し丸めておきます。
⑧
アルミ箔とクリップの間隔が1mm程度離れるように
両面テープで⑦を木板に貼り付けます。
⑨
高電圧発生装置を繋ぐときは
接続箇所に長さ2cmのストローをかぶせて、
接触しても衝撃が起きないようにしておくと安心です。
これで完成で~す!
トグルスイッチを入れ、最初 手で少し回すと、回転を続けます。
①
回している途中で電極の調整をするときは、
絶対に手で触らないで、ストローを使用して下さい。
②
トグルスイッチを切っても、コンデンサに電荷が残っているので暫く回転を続けます。
回転が終わってもまだ電荷が残っているので
電極に触る場合は放電をさせてからにしましょう。
<「高電圧で回るモーター (フランクリンモーターの応用)」の自由研究>
回転する原理は静電気で回る「フランクリンモーター」と同じです。
高電圧発生装置のコンデンサのカソード側から電極(アルミ箔)に負電荷が移動し、
電極と接触したクリップに負電荷を受け渡します。
すると電極、クリップともに負に帯電するので、
クリップはアルミ箔に反発して逃げようとします。
少し離れたところには、コンデンサのアノード側に接続された電極があります。
クリップの負電荷はアノード側の電極に引き寄せられます。
電極間の電位差は大きいために
大きな運動エネルギーを得て、回転をします。
静電気で回る「フランクリンモーター」はこちらをご覧ください。
http://eneene7.blogspot.jp/2016/01/blog-post_35.html